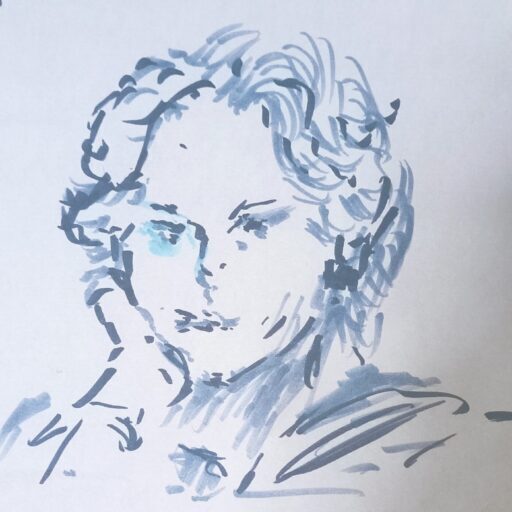弥助侍説の議論について門外漢の放談
弥助侍説の議論について門外漢の放談
下記ブログ記事(以下、「uncorrelated記事」とする)を読んだ。
- 安土桃山時代に日本にいた黒人の英雄化は、DEIともポリコレともウォークとも関係ないよ https://www.anlyznews.com/2025/04/dei_20.html
弥助問題は全く関知していないし、斜め読みしただけだが、覚書。
本事例は、文化盗用問題の一事例と考えることもできるだろう。そして、文化盗用問題の文脈でいうと、「侍にアイデンティティを見出している日本人」の感情もポリコレの文脈から肯定し得ることになろう。つまり、アイデンティティの盗用・簒奪に反倫理性を見出すアイデアはポリコレのアイデアとして既存のものであって1、弥助侍説は、「ある文化やアイデンティティの要素を、別の文化やアイデンティティのメンバーが不適切または無自覚に取り入れること」(wikipedia(文化盗用)2)に當るという主張もあり得る。よって、「弥助侍説を唱えている人々の脅威」を強調する動き自体はポリコレ的な立場からでも正当なものにもなり得るだろう(”強調”が度を超えていれば別の問題になるが)。尤も、本事例では、文化盗用問題を非難する層が、主に反ポリコレ側であるようにみえるという転倒が生じている(?)という点で興味深い。
uncorrelated記事で注目されているのは、議論が感情的になり(?)、DEIやウォークが不正確に槍玉に挙げられていることだが、弥助侍説への非難の動機の少なくない部分がナショナリスティックな情感乃至、反リベラル感情3であろうことを考えると、弥助侍説への非難がときに論理性を欠くことになるのは自然な帰結にも思える4。uncorrelated記事で指南されるような理性的な議論というのを求めるのは、難しいように思えるという諦めに近い感覚もある。また、たしかに、人種的マイノリティをキャストしてコンテンツを再構成するという構図自体は、トランプ二期開始前のリベラル・ポリコレ優勢な情勢ではトレンドであったから、今回の弥助侍説の背後にポリコレやDEIの存在を見出すのも、論理的でないとはいえない。実際に、人種的マイノリティのエンパワーメントに意識的な人々が、弥助侍説に乗っかった例がないことを証明することもできないのであるし、そもそも弥助侍説論争の経緯を、広く合意が取れる形で整理することは難しいように思える(ポストトゥルース時代の議論の一つの典型?)。
さらに厄介なのは、この手の議論はナラティブが積み重なることで、元来考察対象としてきたナラティブの情勢自体が変化し続け、元は、「DEIともポリコレともウォークとも関係な」かったとしても、一定期間後のナラティブの割合は、DEI・ポリコレ・ウォーク関係の議論の比重が増大し、もはや無関係とはいえない様相に変化してしまうことがあるということだろう。斯様に、随時参入してくる外部からの検証や考察が、どんどん内部の考察対象に取り込まれていって、議論全体の勢力図が自己変容してしまうという流れは、ジェンダー論関係の議論でも多く、徒労感が激しい5。例えるならばミイラ取りがミイラになり続けるので、元のミイラが誰であったとか、ミイラ集団全体の変遷だとかビックピクチャを描くことだとかは極めて難しい。この情報量著しい時代において、そういう記録を地道に続けていくということというのは文系研究者へのニーズとしてあるだろう。ポストトゥルース時代とはいっても、ある程度の前提条件となる事実が措定できなければコミュニケーションすら難しくなる。
ポストトゥルース時代では、弥助侍説の歴史実証的な議論で解決がみえるようにも思わないし、uncorrelated記事の試みたように議論の経緯を整理するのも難しいとなると(X(twitter)のuncorrelated記事へは感情的な反発が多い)、結局「弥助侍説を誇張してコンテンツ化することは許容されるか」という根本問題を直接議論する6のが建設的だと思うが、これも結局、その時々のプラットフォームの人々の感覚に左右されるので捗々しい結論は得られなさそうだ。しかしそれでも繰り返しになるが、文化盗用問題などの議論を参考に、できる限り学術的な積み重ねの方法(Wissenschaft)で「弥助侍説を誇張してコンテンツ化することは許容されるか」ということを議論していくしかなく(例えば、法的に許されるか否か、という議論であれば法学の枠組みに当てはめて議論できるだろう7)、その議論をすること自体は社会的に有用なものにも思えなくもないが、悲しいかな逆に分断を産むだけにも思える。
脚注
- クィアベイティングについての猫黒歴史さんの記事を読んで。ーその2|rinp12 https://note.com/rinp12/n/n168ef692bd62 第3節9段落 ↩︎
- 文化の盗用 – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E7%9B%97%E7%94%A8 ↩︎
- その感情自体は、必ずしも非難されるものではない。尚、弥助侍説への反発の動機が「反黒人の人種差別に根差したもの」(uncorrelated記事で紹介の歴史学者の言)であれば、その動機は人権思想的には反倫理的の判を押されることになろうが、、個人的には弥助侍説への反発の動機が「反黒人の人種差別に根差したもの」というのは日本においては不正確に思え、むしろ、反リベラル感情に根差したもののように思う。 ↩︎
- 感情的な反発が起点なので、理由づけはいわばなんでもよいのであろう。ポリコレ批判、DEi批判、文化盗用批判、などなど。使えそうな武器を使うだけである。 ↩︎
- Affirmative Action, Radical feminism, Population | blog rin life https://blog-rin-life.com/affirmative-action-radical-feminism-population/
「アファーマティブアクション(AA)巡る議論など、ジェンダー論フェミニズムは、やっていても意味がないような虚しい気持ちになってくる。そもそもAAが正しいかどうかなどは確定的に定まるわけではなく、例えば明日の議論で国民意識がどう傾くかというような不確定な要素によって、その方策の当不当が流動的に変化するものである。いわば、その方策の正しさを検証しているように見える議論そのものが、アジテーションとして条件をどんどん変えていってしまうという複雑な議論の構造になっている。」 ↩︎ - いわば、事実の措定の議論は諦めて、係争の価値観の確定(価値判断の言語化と共有)の作業に移るのである。いや、そんなことが可能だろうか。判例などが出て確定する領域であれば法的問題は解決するのだが。逆に言えば、結局規範価値の意識の衝突であるように思え、事実の問題は、それぞれの立場の依拠する価値観によって捻じ曲げられていくので、徒労感がある。 ↩︎
- 本来、弥助侍説論争などを検証すべきは表象文化論などの分野の仕事であるようにも思う(?)が、個人的には、ジェンダー論や表象文化論的な分野ではWissenschaftの体裁を成していないものも多いように思う。それ自体問題なのだが。 ↩︎