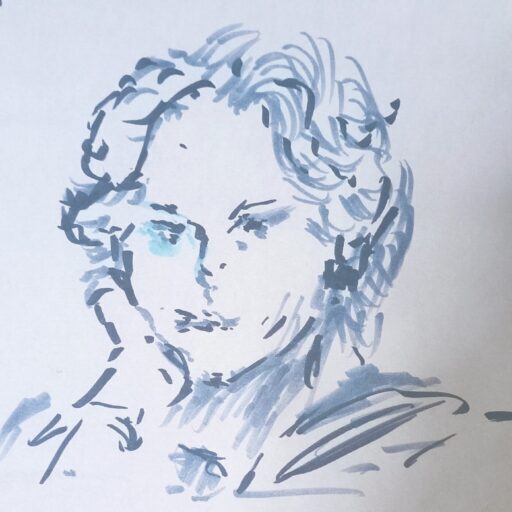規範の正当性を検証しようとする動機を形成する条件について
規範の正当性を検証しようとする動機を形成する条件について
現在、一般に共有されている倫理観については「人権思想」という一つの思想の形態に過ぎず、絶対的なものではないという立場(相対主義的な立場)を私はとっている1。
その立場からすると、現在の教育には驚くべき不気味さがある。なぜなら、「人権思想」というものを絶対的なものとして(洗脳?)教育し、他の可能性について思考させることをしないからである。これは洗脳といってもいいものであるようにも思える。小説『The Giver』も想起させる。
その教育の賜物であるから、当然とも言えるが、現在多くの人が、もはや「人権思想」というものを、数式のように、あるいは顕微鏡を覗けば発見されるもののように絶対的な答えのように自明視していることにも、驚きを覚える。
しかし、仏教という宗教団体に身を置いてみると、上記のような自明視が、人間の脳の作用としてむしろ当然であるということが実感できるような気がする。というのも、僧侶を職業としていると(会社などの組織に身を置く場合も同じであると思うが)、教団の規則や社内規則を履行することに夢中になっていき、それに疑問を持つ機会というのが生じにくいのだ。快楽を追求するというプログラムであると人間を規定すると、なるほど確かに、自分の所属する組織・集団の規範で、安心安全便利快適に生活できている限り、あるいは巨大な危機に直面しないかぎり、その規則を大きく変更しようとする機会・発想が生じにくいのであろう。実際の人間は、一定割合で、「快楽」と関係なく「真実」「正義」を探究する部分があるため、そのような真実探究の動機により、前提規範に疑義を呈す場面が生じ得るのだろうが、思うに、それが発動することは思ったよりも少ない。多くの人間の脳のキャパシティは、自分の生活を成り立たせるために、仕事などを毎日履行するだけで一杯一杯なのかもしれない。思っているよりも、人間の脳のキャパシティは大きくはないのかもしれない。
- 私の相対主義的思想とイスラム的規範 | blog rin life https://blog-rin-life.com/%e7%a7%81%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%af%be%e4%b8%bb%e7%be%a9%e7%9a%84%e6%80%9d%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%a0%e7%9a%84%e8%a6%8f%e7%af%84/ ↩︎