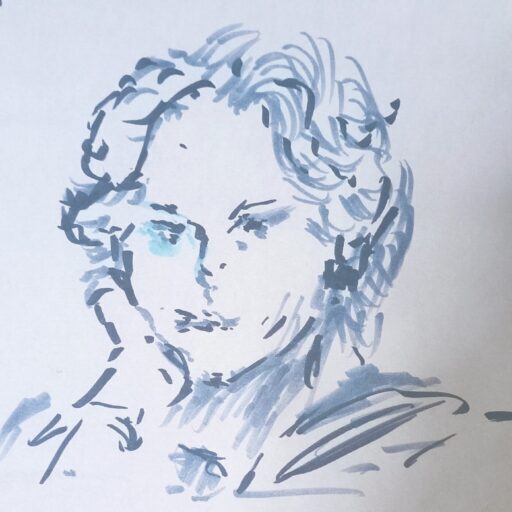覚書
覚書
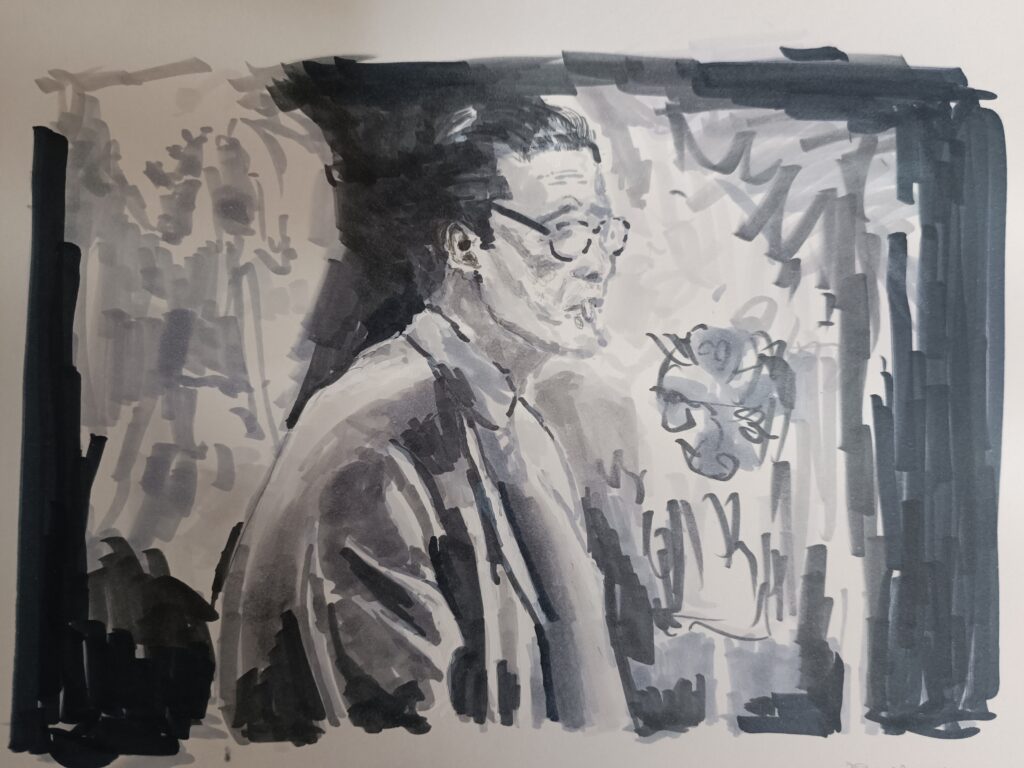
(20241228_16時頃)
フルキエの『「《哲学講義》認識Ⅰ」』を読んでいると以下のような記述があった。
「最後に、現在の知覚もしくはイメージが、過去の知覚の思い出と比較されるとき、思惟による再認がなされる。或る子どものなかに、彼の父親や叔父が子どもの頃にもっていた特徴を見てとるのは、そういうわけである。あるいはまた、映画『ローマの休日』の若き王女アンヌの顔が、新聞に出ているその写真に比較されるのもそういうわけである。」(P.フルキエ, 「《哲学講義》認識Ⅰ」, 1976, 筑摩書房, 176頁)
ここで言及される『ローマの休日』のシーンは映画内開始35分ほどのシーンであると思われる。
(20241228_17時頃)
空の冷たきこと。その冷たさ、空気、空間へのしばしばの突発的な希求と憧憬、回帰願望。
その映画の例。『KILLING EVE』『thelma film 2017』『side effects 2013』『FARGO/ファーゴ』
(20241230_9時頃) カテリーナ・スフォルツァ(Caterina Sforza)(https://w.wiki/3rL3 )
ジローラモが暗殺された際のエピソード(伝説?)は有名である。カテリーナと子どもたちは城外で反乱側に捕えられた。しかし、城の守備隊は降伏しなかった。そこでカテリーナは反乱側には守備隊を説得してくると言って、子どもたちを残し城に入っていった。彼女が城に入ったまま出てこないので、反乱側は人質の子どもたちを殺すと脅した。すると、カテリーナは城館の屋上に立ってスカートを捲り上げると「子どもなどここからいくらでも出てくる」と叫んだのだった。これには反乱側もあっけに取られた。やがて援軍が到着し、反乱は鎮圧された(ただし実際に城壁の上でスカートを捲り上げたかは疑問も残る。城壁の上からでは反乱軍まで声が届くはずがなく、また逆に弓矢で射られる可能性もあるためである)。
カテリーナ・スフォルツァ – Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%84%E3%82%A1)
(20241231_11時頃)
「引用文にある段落を省略する時には、「/」(スラッシュ)を用います。」(他人の作品を引用する時の注意 https://www5f.biglobe.ne.jp/~eLearning/copyright2.html )
(20250115_13:00)
Whataboutism1 法学の論議ではよく行われる手法ではある。
(20250115_16:00 added)
<<<<「男性がするのものであった茶道(茶の湯)が、なぜ女性がするものとなったのか。この問いかけに対し今日考えられている理由は、明治期に入り積極的に女子の学校教育の現場で茶道が取り入れられたからとされる。しかし本当に女学校で積極的な茶道の取り入れは見出せるのであろうか。また、女学校における茶道は作法、という捉え方は的を射たものなのであろうか。」(小林善帆 「茶道と礼法 ———女学校にみるその相関」 平成19年7月7日(茶の湯文化学会会報 No,54 https://www.chanoyu-bunka-gakkai.jp/relays/download/22/48/48/130/?file=/files/libs/130/201809131020558622.pdf))>>>>
(20250121_15:48 added)<<<<<<
by “L’immortelle” (Alain Robbe-Grillet)
00:18:04,367 –>00:18:34,738
N, l’homme:Bonjour
N, l’homme:Fais votre prière?
L, la femme:Non. je m’amusais,
L, la femme:Puis d’ailleurs les femmes n’ont pas le droit de prier à cet endroit.
N, l’homme:Pourquoi donc?
L, la femme:Parce qu’elles sont impures vous ne saviez pas?
L, la femme:Sont à la fois des êtres inférieurs et des démons.
L, la femme:Elles ne sont bonnes que pour faire l’amour.
N, l’homme:こんにちは
N, l’homme:お祈りを?
L, la femme:ふざけていただけ
L, la femme:女性が祈るのは禁止よ
N, l’homme:どうして?
L, la femme:もちろん汚(けが)れているからよ
L, la femme:女性は劣った存在で悪魔なのであり———
L, la femme:取り柄はセックスだけ
※引用箇所について、フランス語はYoutubeの自動文字起こし機能による字幕にrinが訂正を加えたもの。日本語訳は20250121にU-NEXTで配信されていたもので作成者は不明。
>>>>>>
(20250125_14:41 added)<<<<<古文書読解に参考になりそうなブログ
・「奇っ怪な略字・抄物書きの多い写本を買ってみた」 : 砂礫混淆記(http://blog.livedoor.jp/itomata-kokugo/archives/28404552.html )>>>>>>
(20250125_14:42 added) <<<<<<豊島美術館形成における、内藤礼と西沢立衛の仕事の分担
・(内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」 | ブログ | ベネッセアートサイト直島 https://benesse-artsite.jp/story/20230804-2692.html )。>>>>>>
(20250125_14:45 added) <<<<<映画『Tully (タリーと私の秘密の時間)』の中で言及されるゴミの船の話。
Mobro 4000のことだと思われる。
・Mobro 4000 – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Mobro_4000
・Trash Fight: The long voyage of New York’s unwanted garbage barge – New York Daily News (https://www.nydailynews.com/2017/08/14/trash-fight-the-long-voyage-of-new-yorks-unwanted-garbage-barge/)>>>>>
(20250209_07:37) obedienceとHard to Be a God
この老婆と生活してきたというだけで、この老人は尊敬に足るのである。湧き上がる怒りを日々抑えながら。ヘプバーンの”The Nun’s Story”のobedienceやFranny and ZooeyのSeymour’s Fat ladyのことも思い出された。日々の怒りの契機を与え、彼を試しているのだ。一人で生活すると静謐を達成するのは容易だが、知能指数の低い人間と生活すれば、その静謐は容易ではない。Aleksei Germanの”Hard to Be a God”も思い出された。
(20250212_00:49 note added)<<<< 於ツインピークス
於ツインピークスS1#2 34:20 バックグランドミュージックだと思っていた音楽を画角に入ってきた人物が消して、それが劇中機材によるものだと判明する演出。>>>>(20250212_00:49 added note up to here)
(20250220_01:49 note added)<<<< email
Opinion | Ann Patchett: The Decision I Made 30 Years Ago That I Still Regret – The New York Times https://www.nytimes.com/2024/10/15/opinion/ann-patchett-regret-email.html
>>>>(20250220_01:49 added note up to here)
(20250224_09:43 note added)<<<< 金閣寺、付喪神記、時間の凝固
そうだ。たしかにわれわれの生存は、一定のあいだ持続した時間の凝固物に囲まれて保たれていた。たとえば、ただ家事の便に指物師が作った小抽斗も、時を経るにつれ時間がその物の形態を凌駕して、数十年数百年のちには、逆に時間が凝固してその形態をとったかのようになるのである。一定の小さな空間が、はじめは物体によって占められていたのが、凝結した時間によって占められるようになる。それは或る種の霊への化身だ。中世のお伽草子の一つの「付喪神記」の冒頭にはこう書いてある。
「陰陽雑記云、器物百年を経て、化して精霊を得てより、人の心を誑す、これを付喪神と号すといへり。是によりて世俗、毎年立春にさきたちて、人家のふる2具足を、払いたして、路次にすつる事侍り、これを煤払といふ。これ則、百年に一年たらぬ、付喪神の災難にあはしとなり3」
私の行為はかくて付喪神のわざわいに人々の目をひらき、このわざわいから彼らを救うことになろう。(三島由紀夫,『金閣寺』,新潮文庫(み-3-8),247頁 ※ルビは原文ママ。原文の脚注は省略した)
「つくも」とは、「百年に一年たらぬ」と同絵巻の詞書きにあることから「九十九」(つくも)のことであるとされ、『伊勢物語』(第63段)の和歌にみられる老女の白髪をあらわした言葉「つくも髪」を受けて「長い時間(九十九年)」を示していると解釈されている(付喪神 – Wikipedia https://w.wiki/3h2Y )
〽︎百年に一年たらぬつくも髪 我を恋ふらし面影に見ゆ(百年に一年たらぬつくも髪我を恋ふらし面影に見ゆ | 伊勢物語 https://wakastream.jp/article/10000207yloT)
>>>>(20250224_09:43 added note up to this point)
(20250228_12:45 note added)<<<<自己憐憫の悦楽。
自己憐憫の悦楽。いやこの悦楽は自己以外にも向けられる。似た概念としてヒロイズム、感動ポルノ4など。他にもっと良い表現があったようにも思うが思い出せない。
かつてのブログでは以下のようにも書いた。
悲哀のストーリーとしての美意識、ないし美学的意思がそこにあるのだ。私にもある。デカダン、退廃主義への希求にも似る。抑圧の中のわびしさや、切なさ。そういったものが、克服されるべき障害として以上に、それ自体が美しさへのフェティシズムやナルシシズムの対象となる。映画も、昔はそういうものの方が好きだった。フランシスベーコンとか好きだし。David Hamiltonの写真もそういった観点で評価できる。邦画でも似たような寂しさを表現するものは多い。『Blue』(2003)とか。こういう趣味をなんというのだろう。(鬼束ちひろ『蛍』と時間性。そして作品解釈へ〜〜辻恵『放課後の少女たち』、『PERSON of INTEREST 犯罪予知ユニット』、『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』、『Carol (キャロル)』、『Thelma & Louise (テルマ&ルイーズ)』、『The Hours (めぐりあう時間たち)』〜〜 | blog rin life https://blog-rin-life.com/%E9%AC%BC%E6%9D%9F%E3%81%A1%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%80%8E%E8%9B%8D%E3%80%8F%E3%81%A8%E6%99%82%E9%96%93%E6%80%A7%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%9C%E5%93%81%E8%A7%A3%E9%87%88%E3%81%B8%E3%80%9C/ )
>>>>(20250228_12:45 added note up to this point)
(20250502_11:07 note added)<<<<「お2人に 男の子が授かりますように」
『The Godfather』のLuca Brasiの13分15秒頃のセリフ。
「お2人に 男の子が授かりますように」(Prime videoの翻訳、2025/05/03確認)
同15分頃のセリフ
「初めに授かる子は男の子でありますよう」
>>>>(20250502_11:07 added note up to this point)
(20250616_01:41 note added)<<<<「規範的な概念」
「規範的な概念」
私見→事実認定により、判然と決まるようなものではなく、そこに規範的判断が貫入せざるをえないもの。例として、「過失」がある。「出捐」も(法曹時報 58巻1号260頁)。
私見→「規範的」とは単に「べき論=should」のことを示すのではない。判断者の主観的価値観が入り込まざるをえないようなものを、「規範的な概念」といったりする。あるいは単純な客観的要素のみで截然と判断できないような概念を「規範的」と呼ぶこともあるように思える(「出捐」が「規範的な概念」と呼ばれるのは、このような意味においてであろう)。
(20240124作成のゼミ用資料より)
ニャナポニカは次のように主張する「ありのままの注意の光のもとでは、これまで区別されることなく単一の知覚作用に見えていたものが、明晰さが増すにつれて、無数の個々に異なる相(フェーズ)が素早く順番に生起する系列として現れるようになる」のであり、このような「基本的な観察は、やがて真に科学的な観察であることが証明されるだろう」と。
しかし、日々の能動的な知覚は、本当に個々の相(フェーズ)の系列から成り立っているのか、それとも(現在のテーラワーダ仏教の「洞察瞑想」で行うように)じっと坐ったり、あるいはとてもゆっくりと慎重に歩いたりしながらありのままの注意を実践した結果として、連続的な流れであったものが瞬間的な相(フェーズ)の系列に変わるのかを私たちはどうやって知るのだろうか? ありのままの注意は、もともとあった無我の真実を明らかにするのだろうか? それとも無我という規範に合致させるように経験を変化させるのだろうか? 「私が」「私に」「私のもの」という形の経験がなくなるように、自己と心を同一視する見方を解体する方へ私たちを導いているのだろうか? ありのままの注意とは、ものごとを照らし出す光のようなものなのか? それとも、ものごとを形づくる鋳型のようなものなのか?
私が言いたいのは、仏教徒はこれらの疑問に対する答えをもっていないということではない。そうではなく、これらの疑問に対して、単にありのままの注意という経験に訴えるだけでは何の答えにもならないということだ。その答えは、ブッダが説いた「心の教義」、仏教哲学から出てくるものでなければならないが、それは単に記述的であるだけでなく、本来は規範的(価値判断を行うもの)で救済論的(解脱や救済にかかわる)なものなのである。言い換えればありのままの注意を経験すれば、それだけで仏教の心の教義に含まれる記述的真理が確立されるわけではなく、むしろありのままの注意の経験に意味を与えるために、仏教の心の教義が必要になるということだ。仏教の瞑想と仏教の教義はともに歩み、相互に補強し合うものなのだ。
(『仏教は科学なのか 私が仏教徒ではない理由』エヴァン・トンプソン著、58頁)
>>>>(20250616_01:41 added note up to this point)
(20250721_12:37 note added)<<<<「ピタゴラスと鍛冶屋」
「最初の音楽家は鍛治師だった。金属を打つ鋭い音は閉じた空間に亀裂を入れ、それを遠て無限の方角へと飛び去る。そのほとんど暴力的ともいうべきコスミック・ジャンプ。こうして、メタリックな音がコスモスの音楽を生んだ。」(浅田彰『ヘルメスの音楽』3頁)
なぜ、鍛治師?と思っていたが、ピタゴラスと鍛冶屋の逸話からとっているのかと。
>>>>(20250721_12:37 added note up to this point)
(20251013_16:42_note added)<<<映画の作中で行われる、他の映画の、そのままの当該映画としての引用
映画Godfatherの1作目では、Leo McCareyの”The Bells of St. Mary’s”が引用されていた、ingrid bergman出演である。また、woody allenの”annie hall”では、Ingmar Bergmanの”Face to Face”が引用されていた、こちらはliv ullmann出演である。
>>>(20251013_16:42_added note up to this point)
脚注
- (のりふじX on X: “単なるWhataboutismでは。何かを批判するのに類似の何かを批判しないとその権利が生じないなんてことはない。 あと、武力を背景に近隣の領地を刈り取ろうとする日本人はあまりいないが、性風俗に接近する可能性のある日本人は沢山いるので、美化される事による影響は比較にならないと思う。” / X https://x.com/norihuji_x/status/1879369399209189549 ) ↩︎
- rin注:「ふる」は「旧る」だと思われる。 ↩︎
- 「あはじとなり」とするものもある(gakko.edu.mie-u.ac.jp/comp_ed/2004/higashi/tukumo.html https://www.gakko.edu.mie-u.ac.jp/comp_ed/2004/higashi/tukumo.html)。 ↩︎
- 「gastroporn(フードポルノ。視聴者に食欲を誘発するコンテンツ[14][15])のように、英語の「ポルノ(porn)」には、視聴者にある感情などを誘引させることを意図されて作られたコンテンツという意味もある」(「感動ポルノ – Wikipedia」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9F%E5%8B%95%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E ) ↩︎